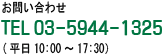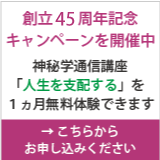バラ十字会 は、宗教や政治のいかなる組織からも独立した歴史ある会員制の哲学団体です。当会は思想の自由を尊重しつつ、神秘哲学、人生哲学、形而上学、心の深奥の探究にご興味をお持ちの方々に、長い年月を経て検証され伝えられてきた知識を、講演、通信講座、雑誌などの形でご提供しています。男性にも女性にも、いかなる人種、宗教、社会的地位の方にも開かれ、「最大の寛容と、厳格な独立」をモットーに世界中で活動している当会は、多くの国々から、非営利公益団体として認められています。

連絡先:バラ十字会日本本部
〒173-0005東京都板橋区仲宿53-2-101
TEL:03-5944-132503-5944-1325
FAX: 03-5944-1326
〒173-0005 東京都板橋区仲宿53-2-101
TEL: 03-5944-132503-5944-1325 (9:30-17:45)
FAX: 03-5944-1326 (終日)
URL: http://www.amorc.or.jp
EMAIL: mail@amorc.or.jp
代表者: 本庄 敦
サイト管理:特定非営利活動(NPO)法人アモールク
(C) Copyright 2003-2014. All right reserved.